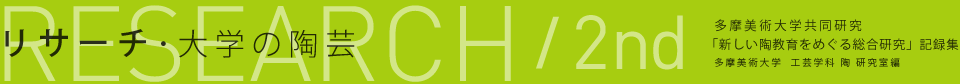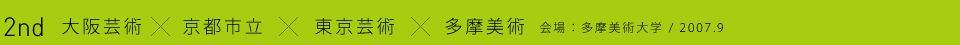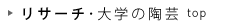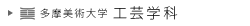4大学におけるこれからの工芸教育について
4-1多摩美の授業
- 井上
-
多摩美の場合、工芸学科の1期生で入ってきた学生たちと、教員との軋轢が面白かったんです。油画陶芸時代の、3年生始めた陶芸と、デザイン志向・工芸志向で入ってきた学生と、違うんですよ。工芸1期生は特にそうだったんですけど、どうして器つくっちゃいけないんだと。そうとは言っていないけど、ぼくの顔に出たらしいんですよ。底があって口があって丸い形をしていれば、やきものとして保証されるとは思わないほうがいいんと諭したんです。そうしたら、ものすごく反発してきたんですよね。
多摩美では、やっぱり最初に陶芸教育が油画科から始めらた経緯と、担当者だった中村錦平の存在というのが、間違いなく大きい。ところが98年の改組で、最初から工芸もしくはやきものをやりたいといって学生が入ってくるようになった。こういうと怒られるけど、錦平先生も、油絵の頃はまだ気楽だったみたいなことをチラとおっしゃっています。油絵の中で、やきものを教えるということは、あるところ学生が自立した表現を求めているという点については保証されているわけなんです。自分が何かをやりたいと思っているファインアート系の学生を相手に、その一つの手段として陶芸、やきものがあるよと、揺さぶりをかける取り組みをしてきたのと違って、そこまで自立した何かを求めるほどの自信もない、というような学生がいたりするのがいまの状況なんですね。
学生の意識を何とか開いていけばと思って、試行錯誤しているところかなあというのが実感なんです。ぼく自身が、大学教育で、やきもののある特化した部分だけしか教わっていないし、産地的な発想も伝統的な発想も、身近なものとしては捉えていない。教員も、どちらかというと表現を主体に考えている。さっきの京都芸大のカリキュラムの編成でいくと、「陶磁器1、2、3」の「3」の部分が中心じゃないか、と。カリキュラムにも、伝統とか技法とかいう言葉は、まずないんじゃないかなあ。
「技術」はあるかもしれないな。とにかく多摩美は、基本的に体験重視、数つくれってことなんですね。1週間に1課題。どんどんつくってことですね。課題を出されて内容に向き合いうんうんと自分で考える。しかも課題自体が、技術の基本を押えていくというよりは、粘土を扱いながら頭を柔らかくして下さいよっていう内容です。1週間に1作ずつ手を動かして形にするという訓練を繰り返していけば、つくる力が身につくだろうという考え方。これが30年近く、ずっと続いてきた基本のやり方で、体験を重ねていけば何か見つかるだろうと。北澤さんの言葉を借りれば、それはエリート教育だと思います。自己創出に根ざしたエリート教育。進学相談会で高校生が、「ここに来たら何になれるんですか」って聞くので、「何でもなれるよ」って答えたんです。この顛末を高校で教えている知り合いに話したら「こんな高い授業料で何いってるんだ、何にも身につけないで追い出すのかよ」って怒られました。でも、尹さんがうまくいっていて、やきものは教材として、「完全食品」だと。これを身につければ何でもできる、と。もちろん、やきものをやって、いろんなこと考えて、作品ができあがって、ものに関わる力みたいなもの、生きていくための基礎力というか、それが身につく。片や作家養成のエリート教育。片や、生きていく力、それをやきものを通して見つけてくれたら、という考えです。
とはいえ、定型を手順を追って辿るわけではないので、学校で何か教えてもらえるとか、技術が身につくと期待していた学生達はビックリして、戸惑っているはずなんです。
例えば、1年生には、まずは何もいわないで課題を出してつくらせてみる。つくってみたら、みんな粘土の塊なんです、やきもののことを知らないわけだから。ほんとうはそれを焼かせてみて結果を確認させれば一番いいんです。そういうことを積み重ねていかれればいいですけど、そこまで時間の余裕がないので、これくらいだったら大丈夫だけど塊は焼くことが難しいんだよ、っていうことくらいは教えています。でもあくまで、つくり方を教えたりとかは、しませんね。それは自分で探すものですよ、という姿勢をまず植えつけようとします。
それと平行して、造形論という授業があって、1、2年に関しては、ぼくら実技の教員が講義の授業や、スライドを紹介したり。だから、東京芸大とは違って、基本的に教員は、しゃべっているんですね。実技課題でも講評がメインなんです。
座学もやるし、頭を使うような内容もやるし、あとは、レポートを書かせます。レポートを書かせて、それについてコメントしたり。そこで学生が頭でっかちになりかねない危険を感じることは感じます。実際は言語化できないこと、体で感じたり、ものでしか語れないかたりって、ありますよね。それをどうやって学生に伝えていくのか、それも問題です。
カリキュラムには轆轤の課題もあるんですよ。ただこの課題は、「轆轤とは何かを考えよう」ということなんですよ。使い方を一応、半日かけてぼくがデモンストレーションするだけ。あとは、各自轆轤使って何か面白いものを探しなさいと。やっぱり皆キョトンとしています。もちろん、形にするには練習、修練も必要です。四苦八苦しながら取り組んで、さらに自分が面白いと思ったことを探してきて、それを手がかりに作品化しなさいという2段階の課題にしてるので、戸惑いながらやっていますよ。
4-2解らないことに向き合う
- 井上
-
「器」を主題、モチーフにした課題も設定しています。昨年は、フィギュア系作品の流行の影響か、人物表現を取り入れた作品が多かったです。機能を考えた学生は、あまりいなかったかなあ。
- 田嶋
-
機能的なものをつくると反則?
- 井上
-
いえいえ、正面から器に対して考えてほしいわけですから、そこに機能があってもよいはずです。反面、壺のフォルムをつくっているけれど、壺のイメージを扱っている学生がいたりします。「器」をどのように捉え、どう解釈することを含めて、課題を出しているんですね。
4年になると、もう自分でテーマ見つけて下さいって、完全にほうり投げるんですけど。ただ、4年の前期は動きが悪い。こちらの意図と矛盾するんですけど、自分で見つける力をつけてほしいってカリキュラムを細かく決め込んでいくと、課題を与えられることに慣れてしまってくる。自分で発想し計画を組立、作品化する入り口で足踏みして取っかかりがすごい悪い。
もちろん、課題のたびに自分のほうに引き寄せて独自に広げられる学生もいるんです。その学生はほっとけばいいんですけど、そうでもない学生がいるのは確か。
教育が平均化したら何も意味はないだろうとは思っていて、同じ内容をどこまで習得したからオッケイ、ということではないので、すごく個別に、いろんなタイプやレベルの学生が出てくる。こちらの方針に、ついてこられなくなる学生もいるのは確かなんです。
- 秋山
-
単位がとれなくって?
- 井上
-
そうじゃなくって、一生懸命やっていても、方向性の違いを感じ取る学生もいるんですよ。ここは違う、これは自分の居場所じゃないと思うんですかね。
いま、世の中がわかりやすさを求める傾向にあるのは確かで、そういえば「ぼんやり思考苦手な若者」というタイトルで作家の森博嗣が朝日新聞に書いいたんですが、いまの若者は抽象化してものを考えられない、具体的なことしか考えられない、と。その人はぼくと同年代なんですけど、若い頃、あまりにも抽象的な話ばかりしているから、もっと具体論で話ができないのかと大人にいわれたっていうんです。でもいまの若い人は、抽象論ができない。ぼくもすごく納得できるんですけどね、わけの分からないものとか、先の見えないものへの力の出し方を知らないなと。美術でも何でも、ものをつくるって、実際何かの役に立つかっていうと、そんな実感はないかもしれない。それを一生懸命やると思えない人が増えている。
- 秋山
-
そういう傾向はあると思いますね。わからないことに向き合う。秩序立てられていないことや、価値が定まっていないことについて向き合うことができない。
- 北澤
-
大きな理念がないから、なんだよね。その場その場で完結していくことの連続というのが、基本的な行動パターンとして若い人にある。
- 井上
-
世の中全体がそうなっている。
- 北澤
-
後期近代社会っていうのはそういうふうになっている。ところで、その問題に入る前に、いま話聞いていて思ったんだけど、多摩美は現代美術やってる。そういう印象があるんだけど、しかし、それは古いタイプの現代美術じゃないかって。要するに、自由画教育の延長というのか……。
- 井上
-
自由画教育?
4-3精神と物質
- 北澤
-
子どもの自発性を大事にしようという、ある意味、自由画教育的発想を純粋かつラディカルに貫いてきたのが、中村錦平さんの指導だったんじゃないか。それをアナーキズムといってもいいけれど、そういうやり方は、すくなくとも教育の場面においては、だんだん時代からのズレを生じ始めているのではないだろうか。
もう一つは、岡本太郎的な対極主義的発想。ここで対極主義というのは、「まず物質がある。片方には精神がある。それをぶつけよう」ということなんだけど、じゃあその媒体は何かといったら身体である、その身体から新しい美術を創造しろ、つくり出せ、というわけだ。つまり、歴史的な意味付けに頼らず、伝統に拘泥せず、身体を媒体として、精神と物質をつなぐ技術を自前でつくり出してゆかなくてはならないという考え方が多摩美の陶にはあったと思う。だけど、これから先も、戦後自由画教育的なアナーキズムだけでやっていけるのかどうか。そのへんをそろそろ反省をすべきではないか。
- 樋口
-
確かに錦平先生が岡本太郎に影響されているのは、よくわかる。
- 北澤
-
その発想を否定する気はないし、歴史的には意味を持ったと思う。ただ、はたして現在も有効か、これからもそうなのか。たとえば大阪芸大も、きょうのお話をうかがった限りでは、対極主義的な精神をどこかで踏まえているなと感じる。ただ、大阪芸大の場合は、それなりに方法論というものがみえる。では、多摩美の場合の方法論とは、はたして何だろう。そこのところがみえない。
- 井上
-
いや、特に現代美術を狙っているわけではないわけですよ。だから、余計にあやふやなことになってしまうのかもしれないけれど。ただ、ものをつくるということを、もっと深いところまでさがって見ることができないか、という部分をやってみたいんです。それを教育じゃないといわれれば、仕方ないという気がするけど、何か決まったものがあって、それを順に教えていくというこということではないんです。
- 北澤
-
ぼくはじつは、多摩美のやり方にシンパシーがある。シンパシーがあるから危惧するわけ。アナーキズムでもいいんだよ。ただ、アナーキズムをどう克服していくのかという工夫は、これから考えなければいけない。これはぼく自身の課題でもある。現代美術は、基本的には精神と物質の対極主義で、ずっとやってきたわけ。しかも、それをつなぐ方法というのは、その都度、自前で編み出していくという形でやってきて、それを多摩美の教育もやっているんだけど、教育の現場に限らず、我々自身が美術の現場で、いまそれでやっていけるのかどうか。これは工芸教育の問題を越える広がりをもつ、ものすごく大きい問題だとぼくは感じている。
- 井上
-
たとえば、ぼくとか秋山さんとか田嶋さんとか、80年代にわりとにぎやかに取り上げられたんですよね。美術の中から見たときに、何か目新しいものないか、と。そこで、何やら面白いことやっているやきものの人たちがいるということでの取り上げられ方だと思います。悪いことではなかったと思うし、自分たちの表現を保証してくれるのは、やっぱり現代美術の考え方だという気もしていたんだけど、あるとき、梯子を外されたわけ。というか、美術の側から消費されたわけです、やきものが。
- 北澤
-
ぼくは、現代美術なんていうのは、そもそも実態があるものじゃなくて、そんなのどこにもないと思っているから。さっきから「現代美術」といっているのは、一種の便宜にすぎない。そもそも「美術」というものが成り立っているかどうかもあやしい。それより「アート」という言葉が、それにとってかわりつつある。「アート」は、技術・芸術・美術という意味を含みますから、言葉の流通からみてゆくと、陶芸も絵画も彫刻もない、そういう状況が到来しつつあるとみることもできる。そういう状況にあって、現代美術と陶芸、工芸という関わりで考えなければいけないというのは、じつは貧しいことなんだ。
だから本来は、「美術」という限定は必要ない、アートでもアルスでも技でもなんでもいい。ただ、いずれにせよ「技」という問題がすごく前面に出てきていると思う。例えば、絵画の復権ということ自体、すでに「技」の回帰だったと気づくべきだった。メディア論という形で、「技」が帰ってきた。つまりそれは、工芸といわれる本来「技」的なジャンルが、がっぷり四つに組める状況がずっと続いてきたということであるわけだ。それは、現代美術に工芸が組み込まれるということでもないし、現代美術が工芸を認めることでもない、もっと広い状況として、そういう事態が到来しているということなんだ。それをどう捉え返すのか、というとき、戦後自由画教育的な、ある意味で造形遊び的な、精神・物質・材料・身体の自前の組織化ということだけで、はたして、やってゆけるのかどうか。それで、広い意味でのアートの状況にコミットできるのだろうか。
- 樋口
-
そういう場が広がって、でも工芸だし、陶芸だし、ということで戻ったり出たり、なかなか難しいものだと思うんですよね。
- 北澤
-
多摩美の工芸学科ができるときに中村錦平さんから相談があって、ぼくは「工芸」だといったんだよ。なぜかというと、要するに、「工芸」という言葉を捉え返し、再定義し、乗り越えてゆけばいい、つまり「工芸」という言葉を消すための工芸学科であればよい、と。言葉だけを変えでもダメで、むしろ工芸という歴史的な言葉を使って何かを起こすところから、工芸自体も変わっていくという相関性を考えるべきで、そこではあえて「工芸」という言葉を使うべきじゃないかと、ぼくは錦平さんに進言したんです。いわばアイロニーとしての「工芸」なんですが、それを、如何にしてカリキュラムに具体化してゆくかは、今後の問題であるように思います。
4-4表現と技術
- 冨田
-
多摩美の陶コースは、技術に重きを置かないというスタンスをいままで守っていますよね。
- 尹
-
教えないということではないです。
- 北澤
-
すでに歴史的に確立された技術ではなくて、精神が物質とぶつかって発生するういういしい技術、それは大切にしてゆく……。
- 尹
-
そうです。技術なり技法がなぜ必要なのかというところを考えて探して、それを試しながら自分なりに習得していくというかたちが大切です。技法や形式や様式を先生から与えられて、それを利用して作りはじめるのではなく、表現したいっていう気持ちの中に技術に向かっていくものがあって、そこが近道とわかったとき、その技術をやればいい、ということなんですね。多くの場合、教育の中でやりやすいのは、まず技法を習得して、その中から進んでいきましょうという方法です。それも確かに一つの方法ですけど、しかし、まず自分たちに作ることや表現することをさせている衝動があることを大切に思いたいです。それを実現するために陶という材料を使うんだということと、その流れや必要に応じて技術や技法があると考えます。中には、「陶じゃないほうが都合がいい」ということもでてきます。そういう場合には、陶以外にこれもあるよ、と。あるいは、陶でやれるところまでやってみよう、ということがある。技術が先ではなく、まずこちら側に、こういう表現があるんだという前提がないと。
- 冨田
-
いまおっしゃったのは、つまり表現主体の教育ということですよね。ただ、それこそ、先ほど北澤さんがおっしゃったような今日的なアートの状況の中で、どれくらい確実なものなのか。表現というものの重要性を、どれくらい共有できているのか、それがどれくらい信じられるものなのか、すごく大きな問題だと思うんですよ。
- 尹
-
それはわかりますが、ここで表現というのは、例えば個人の内面の表現というような枠だけではなくて、もっと広い意味で、作り手が何かを受け手向けて表わしていくということです。そしてその始まりにはやはりまず衝動というか強い欲求があるはずです。その力をてこに実践していく方法論ということです。
- 冨田
-
でも、例えば美大に入ってくる1年生に、はじめからそんな一定量の表現要求があるという確証は、ないですよね。
- 北澤
-
表現欲求の水準を高めてやるということも、無論考えられるけれども、そのことにどういう意義があるのか、それを問うて見る必要があるということだよね。表現ということを内的なものの外在化というふうに捉えるとしたら、そのこと自体どこまで今のアートにおいてインパクトを持ちうるか、ぼくはさっき、そこを疑問視しながら話したんだけれども。例えば、自分自身の内じゃなくて、実は、自分の外に自分がいるのではないかといった考え方もできるわけだし、ランボー流に自分自身が、さまざまな他者であるという考え方もできる。いまの若い世代にとって、アイデンティティそのものが、どこまで成り立ちえているのか、あるいは成り立たなければいけないものなのか。そこを見極めずに、それを強要するとすれば、アイデンティティの専制体制、あるいはアイデンティティ中毒に過ぎないんじゃないのか・・・・といったように、これまで自明とされてきたことを、いろんな次元で疑ってみる必要があると思う。
4-5「もの」と「こと」
- 井上
-
工芸は、ものすごく面白いと思うんです。頭だけじゃない、手だけでもない、ものもある。その関わり合いの中では、意識していても自分の中では答えの出ないことが、たくさんあるわけですよね。ただ、実際につくっている最中には、学生もぼくらも、それに気がついているはずなんです。その面白さに気づくというが意味では、やきものって、すごくいいジャンルだろうと思います。そのやりとりが美術なのか、アートなのか現代美術なのかそれはわからないのですけど、自分がいて、物があって、何かやろうとして関わったんだけど、自分がやっていることのわけがわからない。でもそれが面白いということは、すごくだいじです。学生によくいうのは、頭で考えたっても何も出てこないんだろう、つくれよって。
- 北澤
-
それは、井上くんや尹くんだからできるんだよ、作家だから。ところが、学生がそれをやろうとするときに、いきなり精神と物質を対極化させて、そのあいだで、いきなり身体を働かせてみろっていうのはなあ。どうなんだろうか。それを体系づける方法論が、やはり必要なのではないだろうか。
- 井上
-
いろいろ工夫しているんですよ。ところがいま、それが言葉メインで頭でっかちになっていて、伝わりきらない部分がたくさんある。
- 北澤
-
精神と物質のぶつかり合いということは、ぼくも関心があるし、芸術における大問題として今なお重要だと思うけれども、技術的なレベルのことも、いまは、むしろリアリティがあったりするわけでしょ。工芸学科は、それを油絵や彫刻というほかの学科以上に敏感に感じ取りうるところなんじゃないか。
- 井上
-
例えば、「ものからことへ」と動いている、とかいわれるじゃないですか。確かにそうなんです。「こと」のほうがわかりやすかったりする。けれども、ぼく個人としては、「こと」を表すための「もの」のだいじさがどこかで見失われる危険性を感じている。工芸は、その「もの」と「こと」の両方が連動して成り立っているといえるからこそだいじにしたいな、と。
- 秋山
-
ちなみに、京都芸大1回生の授業で、工芸基礎の意味みたいなことを学生に説明するとき、もちろん陶磁器の話だけをしてもよいのかもしれないですけれども、やっぱりそれでは本来の意味から遠ざかると思って、工芸の話もするんです。工芸といわれている分野の可能性とか特徴について。まあ、ぼくが話をするんですからいい加減なんですけれど、例えば、素材と技術と表現が密接に絡み合っている、だから素材を知る、そしてそれに深く関わっている様々な技術の特徴とか、可能性とか、どういう表現に行き着くかということとかを、いろんな例を示しながら話します。それが工芸じゃないですか、という話です。技術というよりも、技法ですね。技法といったほうが意味が狭いですけども、ただ技法というときには、その視野の中に、そういう技術が切り開いてくれる表現の可能性があるんじゃないか、そこを重視しようという考え方があるんじゃないでしょうか。
たまたま思い出したんですけども、八木一夫先生は、技術なんてのはどうでもいいよ、あとからついてくるから、みたいな話をしょっちゅうされてたんですよ。ところがたまに、ぜんぜん逆に、技術がだいじだともいわれる。要するに、学生に対しては、目指すところがあれば、それに必要なものはおのずと見つけられるという話をしたと思うんですけれども、でも、技術というものが手繰りよせてくれることもあるでしょう。それもわかっておあられたから、逆のことをおっしゃったんだと思うんです。
4-6工芸教育の課題
- 北澤
-
精神さえ自由ならば、技術はあとでついてくる、これは岡本太郎の名言です。しかし、技術にまつわって出てくることもある。ただし、ぼくらはね、いま大学のカリキュラムの話をしているわけで、作家論やっているわけじゃない。物質を通して精神がつかみ取ってくるものはあるんじゃないかといくら言ったって、いまの大学教育で、それは、なかなかむつかしい。大学という教育現場では、もっと別のことを考えなければならない時代が到来しているんじゃないかということだ。
それから、「表現」というと、どうしても自己表現ということを考えてしまう。しかし、「表現」という言葉は多重性を持っていて、presentationの意味もある、representationの意味もある、expressionの意味もある、ものすごく多様な意味をもっている。だから、「表現」という言葉を使ったとき、どの位相でいっているのか、単なる提示なのか、再現なのか、表出なのか、それをはっきりしていかなければならない。ぼくらは、そういう関係の中で表現というものを考えていかなければならない。完全に個人を捨てろというわけではないが、自己表出という意味の表現だけで美術を語っていくわけにがいかない。あるいは、精神と物質を対極化するといういい方をしたとき、その精神が必ずしも、コンピュートする精神なのかというと、ぼくはそうは思わないし、計算不可能な精神だとも思わない。自己の精神の背後には、たぶん、関係性が、社会が、他者が、待ち受けている。物質の向こう側もそう。見えないもの、見えない世界がある。かりに自己表出という言葉を使ったとしても、その自己じたい、ほんとうにあるのかどうか。ぼくたちは、そもそも、そこのところから、ものすごく不安があるんじゃないのか。
- 秋山
-
そこを考えさせてくれるのも、やっぱり工芸の分野なんじゃないですか。ぼく、伝統はきらいなんですけど、やっぱり伝統というもの、歴史とか地域性とか、そういうことは、自己表出だけでは済まないだいじなものとして、密接に絡み合っていますよね。それを教育の現場でどういうふうに触れていくのか、むずかしいところだという気がします。
- 北澤
-
アンソニー・ギデンズっていう社会学者がいっているんですが、自分というものがあって、芸術というものがあって、世界というものがあってと、そうやってアイデンティティをもって考えていくというのは、一種の中毒なんじゃないかと。ただ単に中毒の中で、我々はアイデンティティを求め、エロスを求め、自己というものがあるかのごとく振る舞っているに過ぎないのではじゃないかと。この指摘はかなり決定的なんじゃないか。教育の現場って、世代論の現場でもあるわけで、いま入って来ている若い人たちは、その中毒から逃れようとした世代のさらに次の世代であるわけだ。だから、自己とは何だろうということを、教育の現場にいる者としては考えなければならない。ましてや、現代美術の多摩美であればこそ、それを考えるべきなんじゃないかな。
- 冨田
-
先ほど秋山先生もおっしゃった、技術があって素材があって表現があって、その異なる3つのものを、表現優先、自己優先ではない形で統合していくのが工芸だという考えは、確かにありますよね。そうすることによって、自己表現という価値の限界を超えていく、そういう意味での現代の表現を成立させられるんじゃないか、という発想に基づいて、工芸の可能性を語る。それが、1990年代の工芸論だったと思います。そういう形での工芸の可能性というものを、私も語ろうとしてきたし、その語りに関わってきた。ところが、いま、21世紀になってみたら、もうアートの可能性というか、アートの未来論というものが、異なる要素の統合なんていう方向では語れなくなってきてますよね。例えば、村上隆の『芸術企業論』みたいなものが支持されている状況の中で、「精神と物質の統合」なんていう方面からアートの可能性を考えるのは、すでに、つらいわけです。とすれば、その方向で工芸の可能性を語ってきた、ここ10年の工芸論は何だったのか。それが今後、どれくらい有効で、影響力を保ちうるものなのか。それをアートの未来論のなかにぶつけていくことが、はたしてできるのか。そういう意味で、この10年間の反省というか挫折というか、わたしの中では、ひじょうに強い絶望感があるわけですね。
- 尹
-
もっと教育に絞って考えてみようよ。
- 北澤
-
ただ、まだそこからの教育論っていうのが、打ち立てられてないんだよ。
- 樋口
-
そう、そのバイパスがないんですよ。
- 北澤
-
でも、それが一番やりやすいポジションに、井上君、尹君たちはいるんじゃないの。たとえば、多摩美のいまの陶芸教育の現状は、やっぱり中村錦平路線なんだけど、その次を考えていくときに、何が問題なのかということですよ。ぼくはやっぱり、批判的提唱が必要だと思うけど。
- 井上
-
大きな宿題ありがとうございました。