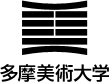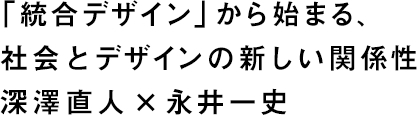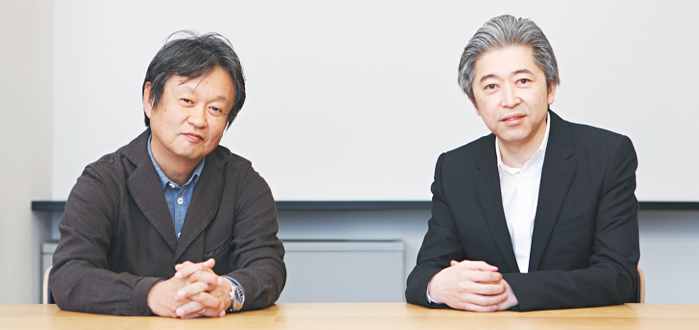
―はじめに、今回新設された学科名の「統合デザイン」というものの考え方について教えていただけますか?
- 深澤
- まず、僕がデザイナーとして働きながら日々感じているのは、「デザイン」というもののとらえ方がとても多様になってきているということです。一方でそれは、デザイン領域の分断と言ってもいいのかもしれません。しかし僕はもともと、それらはすべてつながりあった全体だと考えていたんです。
—深澤先生ご自身が、プロダクトデザイナーとしてあらゆるジャンルのデザインに携わっていますね。その一つひとつが、モノのデザインにある背景や、そこから始まる暮らしを感じさせてくれます。
- 深澤
- 本来デザインとは、人間がいて、モノがあり、空間があって、コミュニケーションがあり、それらが渾然一体となって、生活を成り立たせている場にあるものです。そう考えると、自らのクリエイティビティーを具体化させるメディアやツールを自由に選択できる、そんなキャパシティのあるデザイナーがもっと育ってもいい。統合デザインという言葉には、そういう意味があると思います。
—永井先生はいかがですか? 先生の仕事は、広告などのグラフィックデザインから始まり、現在はブランディングやコミュニケーションデザインでもご活躍中です。
- 永井
 19世紀にヨーロッパでデザインという概念が生まれ、豊かな暮らしに向けて、壁紙や家具などのデザインが登場しました。20世紀に入って生活や産業が急激に発展していく中で、仕事としてのデザインが確立し、グラフィック、プロダクトに分かれ、機能を洗練させてきました。いずれも時代に即したデザインのありようとして、大切な役割を果たしたと言えるでしょう。しかし21世紀の今、大きなデジタル化の波や、成長から成熟への時代の価値観の変化の中で、もう一度、トータルにデザインをとらえなおす時代がきたのではと思っています。
19世紀にヨーロッパでデザインという概念が生まれ、豊かな暮らしに向けて、壁紙や家具などのデザインが登場しました。20世紀に入って生活や産業が急激に発展していく中で、仕事としてのデザインが確立し、グラフィック、プロダクトに分かれ、機能を洗練させてきました。いずれも時代に即したデザインのありようとして、大切な役割を果たしたと言えるでしょう。しかし21世紀の今、大きなデジタル化の波や、成長から成熟への時代の価値観の変化の中で、もう一度、トータルにデザインをとらえなおす時代がきたのではと思っています。
- 深澤
- たとえば永井先生はグラフィック、ブランディング、編集と既に色々なことをされていて、仮にプロダクトデザインの仕事がきても、できる人だと思うんですよ。僕も、建築やコミュニケーションデザインに近いことまで関わって初めて完成する、そんなプロジェクトに常に携わっています。
- 永井
- 統合という意味には縦軸と横軸があるように思います。横軸のデザインとは、例えばあるコップをデザインする場合、パッケージも必要かもしれないし、ブランドロゴも、そのコップを置くお店のデザインもあるかもしれない。デザインの既存の領域を超えていく方向性です。もうひとつの縦軸のデザインとは、我々が生活する中で、様々な問題意識や可能性を感じ、そこからデザインを構想し、リアライズしていく。決まった領域の中で、上手にデザインするのではなく、社会とデザインの関係の中から、自由にデザインを立ち上げる力を持つこと。その両者が重なった「統合デザイン」を考えていくことが大切だと思います。
—そんなお二人をはじめとして、ウェブやインタラクティブデザインで活躍する中村勇吾先生、グラフィックデザインで知られる佐野研二郎先生ら、教授陣の皆さんは現在もクリエイティブの最前線でお仕事をされている方ばかりです。その現場ですでに動き出しているそれぞれの挑戦が、統合デザインであるとも言えそうですね。
- 深澤
- こういう時代に、教育にもそんな姿勢が必要だとの想いはずっと抱いていました。デザインを産業として見たときも、あまりにジャンルやカテゴライズで細かく分断されてしまうと、やはり仕事は疲弊して、だんだん無理も生じてくる。今回、新学科設立において大学側から声をかけてもらった際、そういった自分の課題意識が重なって、引き受けさせてもらうことにしました。僕自身の母校である多摩美でこの挑戦ができる、そのやりがいも感じていますね。
―具体的には、どのようなカリキュラムとなるのでしょう?
- 永井
- 統合デザイン学科では、これまで1-2年次に学んでいた基礎課程と3年次以降に学んでいた専門課程をシームレス(継ぎ目なし)につないだ教育方針が特徴です。グラフィックデザインを例に挙げれば、デッサン、平面構成、タイポグラフィなどの基礎技術を学ぶだけでなく、それらが将来どのように活かされるのかを理解したうえで学んでいけるようにします。また、2年次からは深澤先生を中心とした「統合デザイン論」の講義を通じて、さらにこうした理解を深めていきます。専門課程では「プロジェクト」というゼミ的な講義があり、深澤先生、中村勇吾先生、佐野研二郎先生、私の4名が中心に担当します。前後期で1つずつ、実際にデザイン課題を完成させるプロジェクトを進めていく中で、自らの課題意識をもとに統合的にデザインしていくことを学びます。学生の作品については、我々教員が集まってのクロスレビュー(講評)的なこともやっていく予定です。
- 深澤
 多分野の専門領域クラスがただ集まっただけでは、「統合」やつながりは生まれませんからね。そうではなく、今の世の中は1つのモノをデザインするのにも街を1つデザインするような考え方が必要だったり、人と人のコミュニケーションまで考えてデザインすることが求められる、そういうことを学生に伝えていきたい。逆に、こういう時代だからこそ、どんなデザインでもその先生ごとの切り口、視点から学べるものも多いはずです。僕らも自分の経験をもとに、実際の資料もふんだんに見せながら、デザインについて一緒に考えていきたいです。
多分野の専門領域クラスがただ集まっただけでは、「統合」やつながりは生まれませんからね。そうではなく、今の世の中は1つのモノをデザインするのにも街を1つデザインするような考え方が必要だったり、人と人のコミュニケーションまで考えてデザインすることが求められる、そういうことを学生に伝えていきたい。逆に、こういう時代だからこそ、どんなデザインでもその先生ごとの切り口、視点から学べるものも多いはずです。僕らも自分の経験をもとに、実際の資料もふんだんに見せながら、デザインについて一緒に考えていきたいです。
- 永井
- そうですね。もちろん、個々の教員ごとに専門領域としての主軸はあります。各々の教授がそこを起点にしつつも視野を広げ、より広い領域のデザインを教えていきます。たとえば僕の講義の課題で、あるモノのカタチをどうしたらいいのかというときは深澤先生に相談してみるなど、お互い助言し合える体制をとっていきたいですね。
―そう考えると、1つの専門領域を極めたいという熱意を持った学生にとっても、統合デザイン学科ならではの学びが得られるということでしょうか?
- 永井
- はい。先ほどの横軸・縦軸の話でもわかるかと思いますが、たとえば「茶碗を作る」ことだけを徹底的に突き詰めたいような人を否定するものではありません。モノとしてのかたち作りを超えて、それが使われる社会まで見据えた構想力を持ったデザインを、という考え方ですね。1つのデザインを現代社会の変化も感じながら構想していく力は、特定領域のデザインを志す人々にも有用だと思います。
- 深澤
- つまり、定義付けから始めない、ということでしょうね。自分自身が抱く疑問、達成できないことなど、色んなことをきっかけにデザインを考える。そのとき選択する最適なメディアは、茶碗かもしれないし、映像かもしれません。人々の生活自体が、本来そういうものではないですか? たとえばある街でカフェに入ったとします。そこにはたいてい一番人気の席があって「今日は座れてラッキーだ」といったことがありますよね。それも生活を豊かにするという意味でのクリエイティブだと思うのです。
―ここは素敵な席だな、と思うこと=感性も、ある種の能力?
- 深澤
- そう。さらに、そんな素敵な席がいっぱいあるカフェなら、そこは良い場になるし、会話もはずむ。それが街全体にも作用して……と、ある一点から連鎖していくことも可能なはずです。そして「自分は何となくこの席が好きなだけ」と思っていても、人間が実際に何かを求めるときは、よりファンクショナル(機能的)な要因も大きいと思っています。僕らデザイナーはそういった感覚的な経験を分解して、組み立て直すことを仕事にしています。今、それを教育に置き換えて、若者たちにも提供することができると思うのです。
- 永井
- 関連して言うと、発想する段階だけでなく、その発想の「どれが / どこが」良いのかを「選択すること」も学べる場にしたいですね。色んなことを思いついても、その中で何が本当に良いのかを見極めるのはまた別の力なので、それに気付くことも大切です。
- 深澤
- アイデアやデザインと言うと特殊技能のようだけれど、わかりやすく言えばそれは「気付き」ですよね。あっそうか、という細かなものでもいい。そして永井先生が言うように、気付いただけでなくそれを再現する能力、つまり「具体化する」力を発揮しなくてはいけません。それもこの学科で重視したい大切なことです。
―これからの大学と社会の関係という点では、統合デザイン学科はどのような形でありたいと考えていますか?
- 永井
- 社会に開かれている存在でありたいですね。もちろんそれは、就職のための予備校化という意味ではなく、これからの社会に必要な力を持った人材を育てる場、という意味です。また、学生一人ひとりが何をしたいのか、自分なりのデザインに気付いていくことも社会との大切なつながりだと考えています。こうした前提がないままに、表現や、格好良さだけを追求したデザインがなされることが今の課題な気がします。たとえば前述の「プロジェクト」担当教授4人が一緒に大きな仕事を受けながら、そこに学生たちも参加してもらうということも実現できたらいいなと話しをしています。
- 深澤
- デザインというもの自体を考える研究所というか、そうした存在が今、求められているような気がしているんです。20世紀初頭に生まれたバウハウスは、やはり混沌とした時代に危機感を持った建築家・デザイナーたちを中心として始まった教育機関でしたね。時代は違うけれど、僕はそこに現代のデザインを取り巻く状況と重なるものを感じますし、彼らの行った挑戦には共感しています。バウハウスは日本文化を尊敬し、そこから学んでもいるんです。それは特定のかたちに対してというより、調和や統合というとても複雑なものを、簡潔に、破綻なく実現させる日本の美学に対してだと思います。その特質を僕らや若い皆さんは、DNA的なものとして受け継いでいるのではないでしょうか。
- 永井
- バウハウスは、ウォルター・グロピウス(建築家)や、ヨハネス・イッテンをはじめとしたそれぞれの哲学を持った人が同時期に在籍していたりと、ある種の混沌さもあったのかなと想像します。でも、だからこそ新しい創造性が生まれてきた。統合デザイン学科でも、教授陣は大きくは同じ方角を向いているけれど、個々の問題意識は多様です。だからこそ現実を突破できるリアリティーを獲得できるし、もしかしたら新しいデザインの運動が生まれるきっかけになるかもしれない、という期待はあります。
―教授陣の方々にとっても未知の領域への挑戦という面があるのですね。
- 永井
- もちろん、教育の場として自分の持っている考えやスキルを伝達する役割はきちんと果たすべきですが、教える側の我々がドキドキ、ワクワクしている姿を見せることで、学生たちが学んでくれることもあると思うのです。
- 深澤
- これまで教員をしてきた経験からも、学生と一緒に感動できるのはとても良いことだと実感しています。若い学生からは、こちらが「おおっ!」っとなるとんでもないものや、美術館での体験にもひけをとらない感動をもらえる表現が、急に出てくる。しかも、本人はその凄さを全然わかっていなくて、こちらが先に驚いてしまうという(笑)。でも、それが偶然ではなくできてしまうのは、やはりその人の力ですよね。
―お話からは、新しいデザイナー像をここから生み出していく、そんな先生方の気概を感じます。統合デザイン学科は、どのような志の若者たちを求めているのでしょう。
- 永井
- デザインと社会の新しい関係を生み出せる人材が、今求められていると感じます。彼らが生み出すのは、我々の感性や世界を拡げる発見をもたらすデザインかもしれないし、社会的な課題に真摯に向き合っていくデザインかもしれない。いずれにしても、これまでとは違うことを発想できる人材に期待が集まっています。その点では、たとえば自動車をスタイリングしたいという夢を持った人が統合デザイン学科で学んだ結果、自動車の概念にとらわれない、まったく新しい乗り物が生まれるきっかけになるかもしれない。そういう期待はあります。
- 深澤
- あえて少し視点を変えると、卒業後の将来像として必ずしも「デザイン=ものの作り手」に限らないとも考えています。カフェの話に戻れば、いい席を感じ取れる人が増えていけば、社会全体の豊かさが上がっていくことになるかもしれない。また、中村勇吾先生は「たとえば公務員になる人が出てもいい」という話をしていました(笑)。統合デザイン学科で身に付けたことが「ここをどんな街にしよう」という仕事にも活きるのではないかという考え方ですね。
- 永井
 市役所に勤めたとして「こうやれば行政サービスとしてもっと良くなるんじゃないか」というアイデアを思いつくだけでなく、実際にかたちにできる力が必要ですよね。「考え」と「形」はもちろんつながっているのですが、ある概念が実際に現実世界にかたち作られる際には、実はすごいジャンプが必要なんです。そこを飛び越えられる人がデザイナーだと思っていますし、だからこそ、リアルなものがすごく力を持つ。卒業後の進路に関わらず、そうした力を持った人材が育っていくような場にできたらいいですね。
市役所に勤めたとして「こうやれば行政サービスとしてもっと良くなるんじゃないか」というアイデアを思いつくだけでなく、実際にかたちにできる力が必要ですよね。「考え」と「形」はもちろんつながっているのですが、ある概念が実際に現実世界にかたち作られる際には、実はすごいジャンプが必要なんです。そこを飛び越えられる人がデザイナーだと思っていますし、だからこそ、リアルなものがすごく力を持つ。卒業後の進路に関わらず、そうした力を持った人材が育っていくような場にできたらいいですね。
―これからのデザイナーのあり方も、彼らと社会の関わり方も、様々だということでしょうか。
- 深澤
- ヨーロッパの例を挙げると、向こうでは経営者とデザイナーが直接話し合いながら物事を決めていくんですね。つまり、デザイナーと対話しながらブランドを作る、シンプルなやり方です。経営者たちは自ら生み出すものやその美学に、大きな責任を持っています。そして、デザイナーたちがそんな優れたパートナーに巡り会えると、予想もしない文化が生まれることがある。これは僕の実体験としてあるのですが、日本ではまだそういう感じは少ない。クリエイティブな人たちを受け入れる場が、もっと広がっていいと思うんです。そこにも様々な下地作りが必要だと感じます。これはデザイン界全体を考えるプロセスなので、けっこう大変な仕事です(笑)。でもそれも楽しいことだし、きっと、若い人たちは気付いてくれると思っています。
―最後に、若者たちへのメッセージをお聞かせください。
- 永井
- 実はここで告白すると(笑)、最初に声をかけてもらったとき、先生という重要かつ大変な仕事を、普段の仕事と両立できるか迷いもありました。しかし、深澤さんに「一緒にやろうよ」と誘っていただき、また集まったメンバーの顔ぶれに「ここで何かが生まれる」という可能性を強く感じて、僕も専任教員として参加させてもらうことにしたのです。ですから今は、学生の皆さんと一緒にデザインの新しい挑戦が始められることに、ワクワクしています。
- 深澤
- デザインというのは本質的に、大きな力で何かを派手に動かすものでは決してないと思うんです。むしろ、小さなダイヤルをほんの少し回すだけで、やがて巨大な船がグワーッと動いていくようなイメージが、僕にはあります。そして、誰の中にもスイッチはきっとあると思います。才能ある若者たちに、個々に自分の中のスイッチを見つけてもらえたら嬉しいですね。僕らもそのために自分たちの経験を活かしつつ、すでに色々出し合っている新しいアイデアを、実践していきたいと考えています。