「これから何をデザインすべきなのか?」⑤
教養総合講座B「デザインを話そう。」 第1部
登壇者:永井一史 / 上田壮一 / 宮崎光弘 (担当:木下京子教授)
❺【これからのデザインって何ですか】
――「意識のデザイン」、「反デザイン」、「デザインという生き方」
宮崎:いやいや、すごいなと思いました。最近『AXIS』がリニューアルした号では、「デザインの未来地図と30のキーワード」っていう特集をやったんですけれども、そこにタクラムの田川さんとか日本デザインセンターの原さんとか東大の山中さんとか多摩美の副学長にもなられた深澤さんとか錚々たるメンバーがキーワードを出してくれて、その最後に永井さんに登場していただきました。その記事のキーワードはこの3つだったんですよね。

永井:「これからのデザインって何ですか」っていう、『AXIS』からの問いだったので、いろんな切り⽅はあるなと思ったんですが、その当時、問題意識として感じたことっていうのをまとめたのがこの3つのキーワードなんですね。
1つ⽬が「意識のデザイン」。「グラフィック」、「プロダクト」、「インタラクティブ」そして「システム」など、デザインの領域が拡張されているのは、本で整理したと思うんですが、じゃあここから先どういうデザインっていうことに可能性があるのかって考えた時に、「意識のデザイン」っていうのがあるんじゃないかなって思って。きっかけもあって、上⽥さんから誘っていただいて宮崎さんも⼀緒に⾏ったThink the Earthの後援するイベントで、ヤーコブ・トロールベックさんの講演会でした。この⽅は、SDGsのアイコンをデザインした⽅なんですけども、トロールベックさんがこのままだとSDGsを進めてもなかなか⽬標達成できないんじゃないかと思うと。で、結局⼈の意識が変わっていかないと世界は変わっていかないんじゃないか。そこで、IDGsというインナーデベロップメントゴールを作ったというのをその時聞いて、なるほどと思ったんです。確かに、⼈類が社会的な課題に向き合う時に、こういうことってすごい⼤事だなって思ったんですね。これまでデザインの対象が⼈間を取り巻く環境に対してだったけれど、次のステージというか、どこまでそれをデザインって呼んでいいのかわからないんだけど、⼈間の内側に向かうのではと。今まで倫理とか道徳だとか、ある意味、宗教が担っていたような規範や⼼のあり様をデザインすることが求められていくんじゃないかなっていう⾵に思いました。それが1つ⽬の「意識のデザイン」です。

永井:「反デザイン」っていうのは、きっかけは、ある総合⼤学の博⼠課程の⼤学院⽣に講義をした時で、理系・⽂系を問わず、いろんな学部から学⽣が来ているところで、デザインの話をして「デザインっていうのは世の中よりよくすること」なんだよ、みたいなこと話をしたんですね。講義の終わった後の質問で、別に批判的ということではなく、ニュートラルに「本当にデザインは社会をよくするんですか」みたいなことを何⼈かに質問されて、「ハッ」としたんです。今まで僕⾃⾝、デザインは良くすることだっていう⾵にずっと信じてきて、1mmも疑ってなかった。けれど改めて⾔われた時に「たしかにな」って思ったこともありました。ある種の強制、⼈の意識を変えたり、⾏動変容させるみたいなこと⾃体を、ある種の権⼒構造をあまりいいと思わない⼈たちもいるのかなって思いました。これだけデザインが広がってる中で 、「反デザイン」みたいなことっていうのは、我々デザインの業界もちゃんと受け⽌めて、逆に「反デザイン」に対して、どう「デザイン」ということを説明していくかというロジックや態度をちゃんと考えていかない駄⽬なんじゃないかと思いました。
「デザインという⽣き⽅」っていうのは、ここ10年くらいの流れの中で強く感じていることなんです。もちろん、それぞれの専⾨領域での進化もあるんだけど、それ以上に⼤きいのは、やっぱり「デザインの⺠主化」だと思うんですね。⾔い⽅を変えると、“コモディティ化”とも⾔えるかもしれないけれど。これまではデザインとかデザイナーっていう存在が、ある種のブラックボックスの中にあって、専⾨家だけが扱うものだったのが、今はそうじゃなくなってきた。デジタルツールの進化や、インターネット上のナレッジの広がりもあって、誰もがデザインにアクセスできる時代になってきている。そのこと⾃体は、僕はすごくいいことだと思ってるんです。そうなると、プロフェッショナルが何を担うのかっていう問いも出てくる。その話はまた別の機会にしますね。プロじゃない⼈たちが、⾃分の趣味や仕事にデザイン的な考え⽅を取り込んでいってる状況ですよね。僕⾃⾝、多摩美で社会⼈向けに「クリエイティブ・リーダーシップ・プログラム」っていうプログラムを上野⽑で毎週⼟曜⽇にやってるんですけど、そこに来る⼈たちの反応がすごく興味深くて。「デザイン経営」っていうキーワードを軸にいろんなレクチャーやワークをやるんですが、講座が終わった後に「⼈⽣が変わった」とか、「ものの⾒⽅が変わった」とか、「最近は毎週美術館に⾏ってます」とか、そういう声を聞くことがすごく多いんです。
つまり、デザインって単なる技術や⼿法ではなくて、⽣き⽅や価値観のあり⽅に深く関わっているんだな、と。プロになるとか、ならないとは別のところで、デザインから受け取れるものがちゃんとある。僕は、そういう「デザインの本質的な⼒」が、今まさに社会から求められているしの広がっていることを実感しています。そういうことを、記事に書かせてもらいました。

宮崎:そうですよね、上田さんも読んでいただいたんですよね。どうでしたか?
上田:デザインという生き方は、まさに全然デザインじゃなかった僕がですね、たぶん宮崎さんとか永井さんの影響を受けてすごく関心を持つようになったっていうのはあると思います。学校教育の中でデザインってほとんど学ぶチャンスがないじゃないですか。美術大学に来ない限りは多分デザインを学ぶチャンスってほぼゼロですね。そういう意味で教育がすごく大事だと思っています。意識のデザインっていうのはまさに教育に関わるところだなという風に感じました。永井さんが仰るように危険性もあるのでね。思想統制みたいなことになっちゃうとちょっとまずいんですけど。SDGsのような社会課題を解決して次へステップアップしていく時に、足りていないのは人間の精神性の方だったというのがトロールベックさんがおっしゃってたことですね。そこにちゃんと光を当てていこうという活動がIDGs。だから僕もすごく驚きましたし、確かにそうだと。外側の話だけ一生懸命していても足りなくて、自分たちの内側を成長させていくってことは、すごく大事なポイントだなという風に僕も思いました。
宮崎:僕が永井さんにお聞きしたいのは、永井さんはデザイナーとしてプロ中のプロだと思うので、民主化されていくデザインを見てる時、永井さんにはプロのポジションというのがしっかりある感じがするんですよ。民主化されるデザインの中でデザイナーとして、プロは何をやればいい?プロフェッショナルとして何をデザインすればいいのか?っていうことについてお聞きしたいのですが。
永井:そうですね。僕⾃⾝、⾃分の⼈⽣のなかで、デザインにずいぶん救われてきたという実感があるんです。だからこそ、その体験をできるだけ多くの⼈と共有したいという気持ちがあって、それが「デザインの⺠主化」に関わる⾃分の根本的な動機なんだと思います。だからつい、⼀⽣懸命にそういう活動に取り組んでしまうんです。
ただ、デザインにはまだまだ無限にやることがある。だから「みんながある領域をやるようになったなら、⾃分は別の領域を掘ればいい」と、けっこうシンプルに思ってますね。
宮崎:プロとして新たなことを見つけられる。
永井:プロとして新たな領域をみつけられるのがプロフェッショナルだと思いますけどね。新しい⾃分から視点みたいなものを⾒つけて活動を⽣み出すみたいなこともそうかもしれないし。本当にデザインをやってて思うのは、何から何まで我々デザイナーはデザインとして解釈するので、もうやることは無限にあるから。もちろんそれでちゃんとビジネスとしてどれだけ成⽴させるかっていうのは、もう1つのハードルかもしれないのだけれど、やることがなくなるってことはもう全くないので。そこはまったく⼼配してないですね。どうですか宮崎さん。
宮崎:なんとなく僕もそうかなって思いました。この前、佐藤卓さんに講義に来てもらったんですけど、「デザインとは?」っていう、すごくシンプルな学生の質問に対して一言で「気遣い」って言ったんですよ。
永井:あ、そうなんですか。僕が聞いた時と違うこと言ってる(笑)。
宮崎:気遣える力がなければ、気遣えないわけなんで。ただ気遣いだと思ってるんじゃなくて、ちゃんと力がある人が気遣えるってところが、すごく重要なんだろうなっていう風に思いました。 時間が迫ってきてるので、ちょっと上田さんの話を聞こうと思ってます。
上田:いやいや、もう飛ばしていただいてもいいんですけど。
これから必要なのは「控えめな創造力(Humble Creativity)」
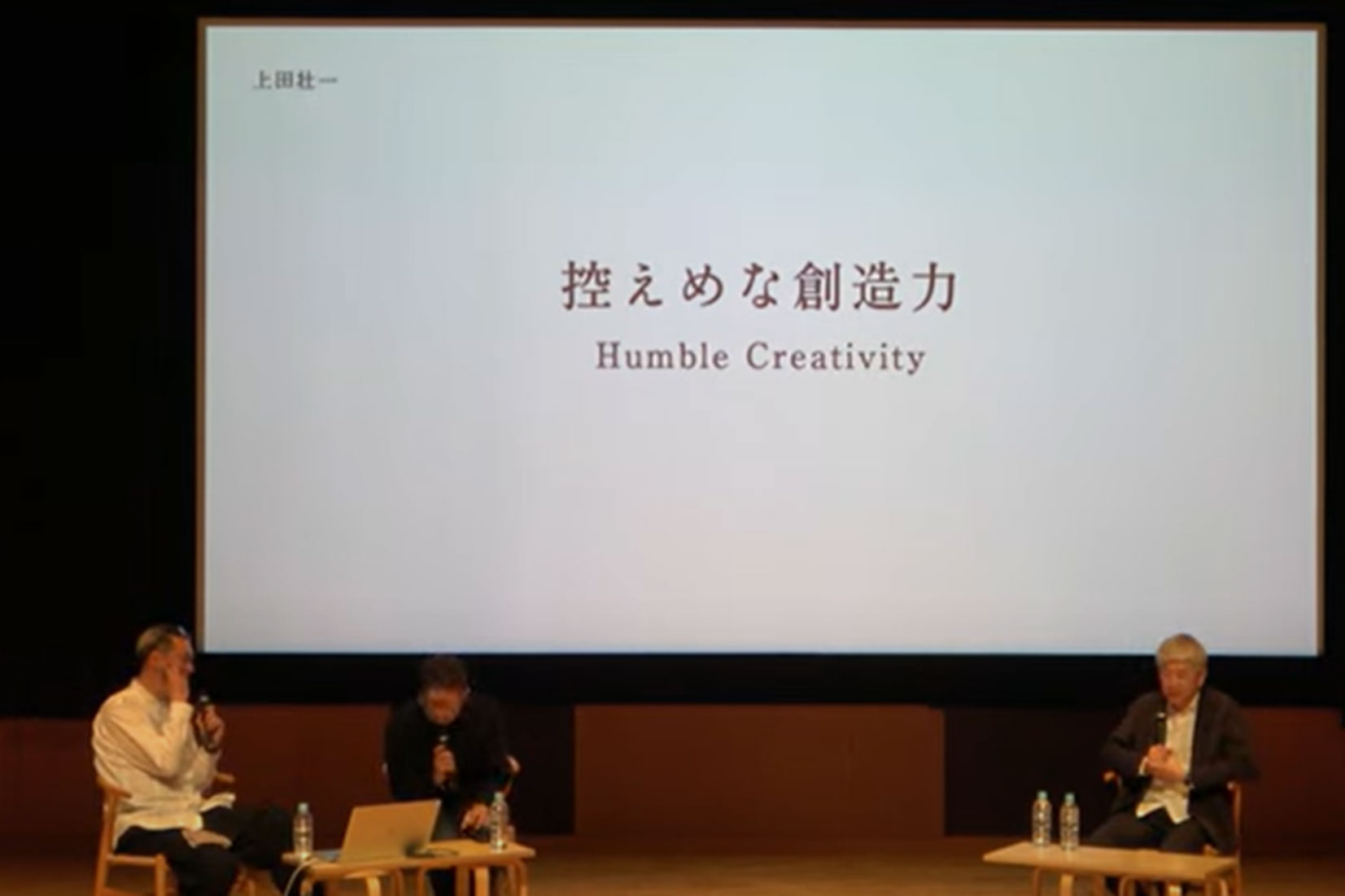
上田:これは実は僕の言葉ではなくて、イタリアのローマにいらっしゃる多木陽介さんという批評家であり舞台演出家でもあるんですけども、彼が追いかけているテーマで。僕自身もすごく共感していて、日本語に訳すと「控えめな創造力」、英語だと「Humble Creativity」という言葉なんですね。説明するとすごく長くなってしまうんですけど。多木さんがつい最近本を書いたんですよ。まさに「控えめな創造力」というテーマの。「イタリアンデザインの静かな革命」という副題で。彼は元々アキッレ・カスティリオーニさんの研究から始めていくんですけども。今では巨匠と言われるブルーノ・ムナーリさんだったりとかエンツォ・マーリさんだったりとか、そういう人たちの仕事ぶりを知れば知るほど、まさにこの「控えめな創造力」を体現しているんだということが分かってきて。しかもそれが今失われようとしていると。最先端のデザインの世界だったり、クリエイティブな世界から失われようとしているという危機感もあって。

上田:この右の写真は、今年の3月にイタリアに僕らが高校や中学の先生を誘って「控えめな創造力」の源流を体感しに、ミラノ周辺のいろいろな人たちを訪ね歩く旅をした時の写真です。黄色い袖の方が多木陽介さんですね。その右側にいらっしゃるのがシルヴァーナ・スペラーティさん。ブルーノ・ムナーリさんは晩年にライフワークとして幼児教育のメソッドをいっぱい作られて、そのメソッドの継承者でもありブルーノ・ムナーリ協会の会長さんでもある方です。彼女のワークショップを体験しに行くことが旅の目的の1つでした。「控えめな創造力」って何かって言うと、言葉から直感的に分かる方はすごくいらっしゃると思うんですけど、今のクリエイティビティがどうしても「進歩」とか、「資本主義的なお金」とかですね、そういう前へ前へという方向へどんどん引っ張られていっているし、多分皆さんも目指していくんだと思います。それはそれでいいと思うんですけども、でも一方で先ほどの『百年の愚行』という写真集のように、過去を振り返って自らの過ちの反省した上で未来を見るという態度もそうかもしれないし、ポール・スポング博士がシャチを捕まえてきて研究するのでなくて、シャチのいる場所にそっと自分たちが立って、まさに控えめな態度でその生態を見るっていう。そういう態度を忘れないでいよう、どちらも同じぐらいの強さで持っていた方が、社会はもっと健全な姿で前に行くよねっていう。そういうことを多木さんおっしゃってるんですね。今、サステナビリティってすごく大きな教育のテーマになっているんですけど、学校の先生が教えられるのは課題ばっかりなんですよ。世界でこんなことが起きてますと。今世界はこんな大変なことになってますとか、温暖化のメカニズムはこうですとか、化石燃料を減らさなきゃいけませんとかっていうのは知識として教えることはできます。でもいざ、ではどう行動していけばいいのかってなった時に、クリエイティビティやイマジネーションなど、イノベーションにつながるような教育が大事になってきます。その時に、多木さんが「気遣い」や「優しさ」っておっしゃったような、真に優れたデザイナーたちが兼ね備えている控えめさとか謙虚さみたいなところも含めた創造性を伝えていくことが、教育においてはすごく大事なポイントなんじゃないかなと思って。それに共感する教員の方たちもたくさんいらっしゃって、クリエイティビティについては学校でもこれから取り組んでいかなきゃいけないけれども、でもどう教えたらいいのかがわかんないっていう中に、このキーワードにはすごく深いヒントがあるんじゃないかなと思って、教育者の方たちと一緒になって今まさに探究をしているところです。日本にも同じような「控えめな創造力」を発揮して活動されているデザイナーが各地にいらっしゃるので。国内での旅も企画をして、いろんな地域や人に会いに行こうとしているところですね。
宮崎:どうですか、永井さん。

永井:そうですね。面白いですね。元々デザインっていう言葉自体がイタリアに入る前は「プロジェッタ」っていう「プロジェクト」って呼んでたってことですね。
上田:デザインはイタリアでは外来語なんですね。
永井:で。結局、社会をより良くしていくために、そのプロジェクトっていうのを多分起こしていくっていうことだと思うんですけど。考えてみると、やっぱり近代デザイン、ウィリアム・モリスとかジョン・ラスキンだとかなんかそこら辺の⼈が⾔ってたこともまさにきっとそういうことですよね。その現状に対するオルタナティブとして実は近代デザインっていうのは⽴ち上がってるんだけど。良くも悪くも産業とか経済の枠組みの中に⼊ってるんだけど、それはそれで⼀定の役割を果たしてんだけど、それだけじゃなくて、本質的にオルタナティブとしての思想みたいなことは、こういう時代だからこそまた求められるのかなっていう気がします。
上田:そうですね。それが新しいというよりは先ほど言ったように、災害で街が破壊された時に出てくる、人が誰もが持っている創造性だとか、そっちに近いものなのかなっていうのがあって。すごいクリエイターが最後にたどり着く境地としての控えめな創造力ではなくて、誰もが持っている元々あった創造力みたいなところとすごく近しいんじゃないかと。人間として普通に生きてくために使おうとしている創造力っていうか。なんかその辺りも今の「デザインとしての生き方」ともすごくつながる話かなと思いますね。
宮崎:そうですね。「デザインとしての生き方」に近いものを感じました。時間が迫ってきたので最後に。
「デザインを守ってください(Please protect design)」何を守るの?

宮崎:私の言葉は「デザインを守ってください(Please protect design)」。これは僕の言葉じゃなくて、実は今回の展覧会でこのエットレ・ソットサスさんっていう人が1997年、今から27 年前に1番最初に『AXIS』の表紙シリーズで登場してもらって、その時にサインを書いてもらったのですが、その時にさらっと書いたのがこの言葉でした、四半世紀も前に。

宮崎:PLEASE PROTECT DESIGN(NOT INDSUSTRY, NOT COMMERCE, NOT ONLY MONEY...)PLEASE PROTECT SOLITUDE, MISTERY, CALM, UNKNOWN, POETORY, ..................LIFE, .........THANK YOU... LOVE ETTORE(SOTTSASS) 最後のLOVEが可愛いんですけれども。この言葉が意味しているもの、僕は本当の真意は分からないんです。ソットサスさんがなぜ27年前にこれを書いたのか。ただソットサスさん自身は、実は経済に貢献するデザインをめちゃくちゃやってきた人なんですね。

宮崎:このオリベッティのバレンタインっていうタイプライターは、めちゃくちゃ売れたんですね。事務機器としてこんなに美しくて、こんなに気持ちいいものはないっていうぐらい。昔のAppleコンピューターみたいな感じで。晩年はポストモダンデザインになっていく。それでもすごく経済活動の中でのデザインというのを十分に理解した上でこの言葉を言っている。なのでやっぱりすごく深い言葉だなって僕は思っていて。今回の展覧会でもファイルの中にこの言葉を入れさせていただいたんですけども。だから僕はこれを理解してるっていうよりは、この言葉について考えていきたいっていう。これはソットサスさんが何を言ってくれたんだろうと。今27年経って、「デザインを守れ」っていうのは何を守るんだっていうことを、なんかすごい自分の中では今でも気になっている言葉です。もしかしたらその「デザインという生き方」とか「控えめな創造力」っていうのにも少し繋がるのかもしれないなという風には思っています。
永井:それでは素晴らしい締めになったところで。
宮崎:これで終わっちゃっていいですかね? では、ありがとうございました。少し伸びましたけれど、これで第1部を終わりたいと思います。
▼続きは以下のリンクからご覧ください。