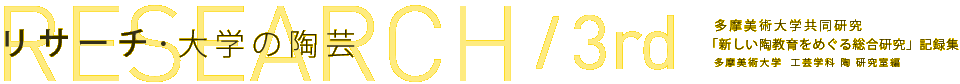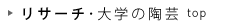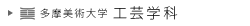4それぞれの主張

4-1つくる理由
- 中島
-
僕は、動機は学生の中にあると思っています。社会が求めていたり役立つためにものを作ってるんじゃなくって、つくらなければならない自分がいるわけで、それを自覚するかどうかという話をしてる。やっぱり、現代社会の中で生きている己に、どうしてもつくりたい衝動が湧いてくる、それがないと。
- 井上
-
自分がやりたいことを提示していくことに、その存在意義があるんだけれど。
- 中島
-
幸せといえば、世の中のためになったり、価値があって食べられればなおかつ良いけど、その前に自分に問題がある。それを共有できる人たちもいるっていう気がするんですよね。
- 小松
-
かつて、北欧で「アーティストはアトリエにこもっていてはいけない、デザイナーと一緒になって、社会との関わりをもっと持たなくちゃいけない」という運動があって、デザインの名品がたくさん生まれ現在も残っていますが、アーティストが個人で磨いた感性を、日常のものにつぎ込んだ時代があった。そういう観点からいくと、日本には陶芸家でいい作品をつくる人が一杯いるわけですが、日常的なものってそんなに面白いものがないんですよね。どちらかというと、もっと面白いことが一杯あるから陶芸家はそちらへばかり行っちゃいます。もう少し日常的なものに磨かれた感性を発揮してもらいたい、というのが私の希望としてあります。
- 尹
-
僕は多摩美のカリキュラムを考える時に、器物を作ることにも、表現に走ることにも、どちらにでもきっかけにできるように組み立てます。つまり「解釈する力」を持ってほしいというか。だからどんな課題にも、器で答える人が出てほしいし、あるいはそんなの興味ないというのもあり。卒業後に陶でつくることを止めたっていいとも思っています。ただ、やきもので何かを作ってきたことを通して、「つくる力」、「考える力」を鍛えて、それを堂々と他の仕事で使ってもらいたい。
- 中島
-
そうじゃなくて、つくらざるを得ない何かがあるわけでしょう。だから、やきものを選んだり、美術を選んだり、何かをつくりながら続けて行きたいと、学生が入ってくるわけで。
- 尹
-
それを気付かせるのがカリキュラムですよね。
- 中島
-
でも変だけど、自覚したばかりに困ってしまう、その子のパンドラの箱を開けちゃって責任を取れるかっていう悩みもあるんです。「赤信号は止まりましょう」と止まる子に、車がいなければ渡ってもいいかも、ってことを気付かせていいのか。
- 井上
-
極端に言えば、気付いていない人の方が多いかもしれない。中島先生のように引き出せるってびっくりするんだけど、条件が整っているにもかかわらず、積極的にやらない。それは切迫してないってことですね。
多摩美にきた子たちの中にもいるんです。もう既に開いている学生がいる。つくり続ける資質があり、うまくやれば作家になっていく素養があって、そういう人は放っておいてもいい。むしろさっき言った、うまいけど自分の中から打ち出していくことができない、なかなかつくれず苦労してる子が美大にはたくさんいるんですよ。ずっと続けていって、結果を見て自分にフィードバックして、また中に貯めて。貯めるのが深ければ深いほど出てくるのが大きいはず。
何かと関わりながら自分をつくりあげ、課題をもってつくり続けて行くことは力になるってことです。「やきもので培った力」が他のことの力にならないはずはない、そういう意味でなんらかの「生きていく力」にはなるかもしれない。
4-2学びの応用
- 尹
-
美術大学が、社会のなかで維持されるべき理由があるとしたら、音楽や体育もそうだけど、人が生きていくうえで根源的に持っている力を、鮮明にさせて、もっと伸ばしていって、できればそれを社会のために役立てよう、そういう段階があると思います。その根源的な力に気が付く方法はいろいろで、音楽で気が付く人や、スポーツ出来がつく人がいるように、ある種の人は造形物で気が付いて、その中でも鉄をがんがん叩かないと気が付かない人がいれば、やきもので粘土をグニュグニュ触って、という人もいる。粘土はそんな力を引き出しやすい材料だと思っています。粘土で作ったものを焼いて硬くすると、縮んで変形して不都合が起こる。それをどう納めながら作っていくのか、その過程で自分の深いところにあるものに気が付いたり、そのバランスを取ることに苦労したりしながら、気が付いたことを社会に還元する。ものすごく長いプロセスですけど、つまりカリキュラムというのは、そこら辺をできるだけ掬い取るような、そうありたいなと願っています。だから器か、いわゆるオブジェかは、もう乗せる舟の問題。たとえばうちの学生が卒業してハンカチのデザイナーになったとして、やきものを扱うことで身に付けた力を、現場の仕事に力強く込められると思います。現場の状況に応じて、その場でなんとかしていく力、状況を活かして何かにつくりあげる力。多分これは「ものをつくる力」じゃないかな。美大の卒業生が社会に向けて堂々と提示できるものはこれが一番じゃないかなって気がしています。課題の繰り返しの中で、そんな力をつけてもらいたい、と僕らはカリキュラムを作成する時に気にしてます。
- 北澤
-
応用力だよね。気付かせるとか、あるいは止むに止まれずにつくるなんていうのは、いわば心理カウンセリングか診療内科みたいなもので、僕はそんなことは美術大学の仕事だとは思わない。それを気付かせることも、結局はそれをどう社会的に応用するかに結びつけることで意義をもつということがわかってないと、表現主義になっちゃう。あるいは心理カウンセリング、臨床心理学と同じになってしまうと思う。
- 尹
-
もちろんそう。それを能力として抑えこんでいくという。
- 北澤
-
今の話のポイントはそこだよね。応用っていうことだよね。応用の効果はある。
- 尹
-
そして、学校ごとに応用させ方のウェイトバランスがあるべきと思います。
- 井上
-
ずっときっかけづくりをしてる。カリキュラムって、関わりの持ち方の手がかりやチャンスを提供する。チャンスはいらない場合も多いんだけど、いろいろ手を替え品を替えながら提示して。それで、ある人は早いうちに気が付くし、まったく気付かない人もいる。
- 尹
-
あとで気が付く、そういう人もいますよね。
- 井上
-
だって僕なんて、学生時代に言われたことは2つぐらいしか覚えてない。だから僕らは一生懸命授業で話しているけれど、まったく覚えてない学生もいるだろうし、あの時あんなことを言っていたなあと10年後に思い出す卒業生もいるだろうし。そういうことをやっているのかもしれない。
- 冨田
-
中島さんは少し違いませんか。
- 中島
-
さきほどのように、「作家をつくる」と言われるとドキっとする。いや、僕はそんなつもりはありません。良いやきもの見て、感動するっていうふうに楽しくいきたいんだけど、ついつい……。
- 井上
-
でも、どこかで方向性を打たなきゃいけない。たとえば、いろんな人のためにいろんなタイプのカリキュラムを用意して、個別に対応していくなんてあり得ないでしょ。中島さんが言われたように、実際、全員が作家にはならない。
しかし作家養成で僕はいいと思う。極端に作家養成をしていく中で、ついてこれない子もいるし戸惑う子もいるし、思わずパンドラの箱を開けられちゃう子もいる。その人たちが3年もしくは4年の間で関わり、培ってきたことは、横柄な意味ではなく、極端な作家養成をやろうとしているから故についてくる力だと思う。
4-3美術大学の矛盾
- 北澤
-
「美術の教育」と「美術による教育」。美術によって人間的なものを深める、育てるなんて、芸術の観点からみれば、ひどくヤワなことだと思う。しかし、根本に立ち返れば、それが一番たいせつなことなのかもしれない。だから、「美術による教育」を主張することは、もしかするとパンドラの箱をあけることなのかもしれない。しかし、「美術の教育」を掲げる実技系大学としては、危険も大きい。にもかかわらず、敢えて、そうしなければ美術大学は成り立たない。矛盾ですよ。つまりこれは美術大学というものの矛盾ですよ。
- 中島
-
矛盾ですよ。矛盾の中でやってる。
- 北澤
-
そうですよね。だから先生個人の悩みというより……。
- 冨田
-
だからそれは多分、美術に理解がある主婦をつくるということでは解消できない。それは方便としてでも解消できない。
- 井上
-
じゃあ出口としては何が一番。
- 山本
-
そんなの責任を持てるのかなあ。
- 右澤
-
実のところ、信号を守る人が赤でも渡れるようになったということと、信号を守れなかった人が美術を学ぶことによって信号を守れるようになるということは同じかも知れない。(笑)
- 井上
-
あり得るかもしれない。だって自分のことをちゃんと社会で成り立たせようとしたら、ものすごく現実的になって、パンドラの箱を開けられただけではすまなくなって、今度はしっかりと社会性を身に付けないと続けることはできない。「つくる力」がある子と「続ける力」がある子って、まったく同じではないんですよね。だから箱を開けた子が、ずっと続けているかはわからない。そこは一致する子と一致しない子がやっぱりいる。
4-4工芸工業デザイン
- 冨田
-
武蔵美には、「工芸工業デザイン」という枠がありますよね。すごく特徴ある枠だと思うんですけど、少なくとも工業デザインに関しては、明らかに規模も水準も、それができた50年前と今とではまったく別なものになってると思うんですよ。そういう中で、工芸デザインの方の変容とか、行く末について、どうお考えですか。
- 小松
-
大雑把な言い方になりますが、以前からデザインは企業の利潤追求のためにあって、今でも続いています。そのようなものづくりの結果が地球規模の環境のひずみにつながってきています。そこを見直して“人”中心のものづくりが最優先されなければなりません。
- 井上
-
多摩美では図案科がグラフィックデザイン科になったのが1960年代。そこから枝分れでデザイン系が細分化して。それで、プロダクト系の学生でやきものの食器のデザイナーになる子がいるんですよ。ただ実際に器を作ったことがない人たちが、デザイナーになっている。誤解していたのは、武蔵美はその両方を結構バランスよくやって、片や作りながら、片やそういうプロダクト的な教育を重点的にやっていらして、企業デザイナー的な人たちを育てているのかなあと思ったら、以外と作ることへ、かなりのウェイトが占められていて……。プレゼンの課題もあるんですけど、実作のあとからついてきている。
- 冨田
-
私もそういう勝手な思い込みがありました。
- 井上
-
「工芸工業デザイン」という学科名から、実作を重視したプロダクトというような認識を勝手にしていたのは確かですね。これはちょっと誤解していました。それ以外の、もう少し身近な数量品的なことも含まれているのか、特別な生活じゃなくて、身近な生活というところを考えているのか。そうかと言って量産でもないし。昔でいったらクラフトの感じですよね。
- 小松
-
そうですね、特に素材別のコースに分かれてからは、手工業的な物づくりを中心に指導していると言えます。
- 井上
-
まあ、たくさんでもないし、一品でもないし、というところをやっぱりまだ。
- 尹
-
なくならない領域ですよね、一品ものと量産ものの間というのは。ふさわしい作り方や、スピリットやマインドなどが、多分いろいろあるはずなので。
4-5「工芸的」リアリティ
- 北澤
-
リアリティって何かというと、複合的な感覚が整合するかどうかですよね。見た目と触覚が矛盾しない。重そうなものを手にしたときに、重いって感じたらリアル。茶碗を手にして、それを眺める。このときに起こっているのが感覚の複合です。しかし、パソコンの液晶画面に入り浸りの人たちはリアルなものを実感する感覚の軸が足りていない。物質とのベーシックな複合感覚的なやりとりがない。こうした複合感覚を「工芸的」と称することもないけれど、それを工芸が、たとえば茶碗を作ることで保持してきたことも事実だ。
- 尹
-
陶という材料で何かを作るためには、複雑な手順をこなしていかなければできませんね。でもその作る過程のなかで感じるウキウキとした感覚を引っぱり出そうとする訓練は、それは筋力を鍛えるように、その人の何かの力を太くしていけるんじゃないかと思っています。学生を見ていると、その感覚がどんどん太くなっていくのが見えてきますよね。以前、ある建築事務所で、コンペに提出する模型を作るために人手が必要で、うちの陶の学生が10人近くバイトに呼ばれて、他大学の建築学科の学生と一緒に長期間働いたことがありました。彼らを呼んだ建築家の方があとで「多摩美の学生たちのワイルドさと発想のバラバラさ」を褒めてくれました。例えば、街路樹の模型を作るのに、建築学科の学生は、かすみ草を緑に染めた既成のもので何とかしようとするところを、多摩美の子たちは、バッーと外に出かけて何か拾ってきて、それぞれに何か作ったそうです。下手なのもあったとは思いますが、やきものとは関係なくても、その場でなんとか作っていく力が、運良くバイトの中で社会化できた場面だった。(笑)
- 井上
-
前回もそうなんですけど、ある意味でわかっているつもりだった「工芸教育」、「陶芸教育」。近い存在の学校でありながら誤解をしていて、聞いてみないとわからない部分がある。いろんな大学でひと色ではない「工芸教育」、「陶芸教育」が続いていくということが、やっぱり大切なことのような気がしますね。差異がなければ、その存在理由がないのではないかという。もちろんどこの学校も揺れ続けるはずなので、状況としては平坦ではない。また機会があったらそういうところをお話しできればと。なかなかね、見つからないんですね、いい答えは。
- 尹
-
それぞれの学校が背負っている状況が違うことが大事だし、状況の違いをそれぞれがうまく提示できて、学生はそれを選べるのが理想です。
- 井上
-
共同で分かりやすく学校の違いみたいなものを提示して、あなたはどこ選ぶのっていうぐらいなものにこの研究が発展出来ればいいのですが。
武蔵美の「工芸工業」という名前からの印象にも誤解があったように、多摩美の工芸をもっと積極的に出していかないといけないのかなと。必ずしも外部のイメージと一致してないっていうのはひしひしと感じました。